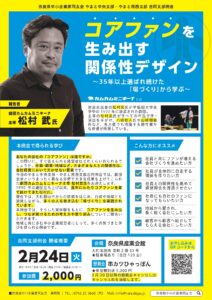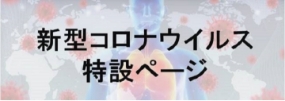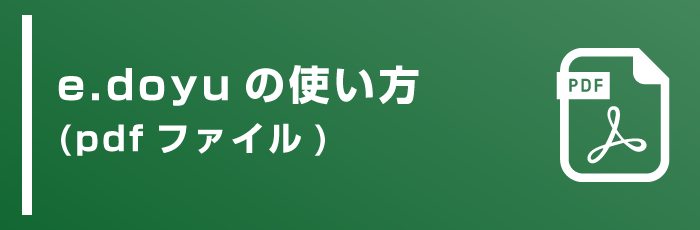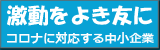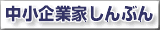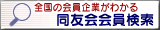やまと中央支部と障害者共働委員会合同8月例会では、神奈川同友会の(株)障碍社・安藤信哉さんを報告者にお迎えし、「超二流企業を目指します~エクセレントではなくグッドで~」をテーマに、経営体験報告をいただきました。
安藤さんご自身、十代のころに交通事故で脊髄損傷を負われ、車いすでの生活をされています。その経験を経て「重度な障害があっても自由に暮らしたい」という想いから、2005年9月に創業されました。
重度訪問介護・居宅介護・資格講習・B型支援・福祉用具事業など、様々な挑戦と失敗を繰り返され、今では年商11.5億円、社員数340名の会社へと成長されています。会社が成長してきたからこそできる未来を目指し、常に考えながら日々の経営を進められています。
「自由 豊かさ 共生」を経営理念とし、それを実現するために10の経営方針を社員と共に策定。障害の有無にかかわらず、社会で生きるすべての人が「生きていて良かった」と思える人生にしていくために、本気で考え抜いた結果、今までにないビジネスモデルも生み出されました。
その積み重ねは、「第3回東京同友会『人を生かす経営』大賞」や「第12回日本でいちばん大切にしたい会社大賞 厚生労働大臣賞」など数々の受賞につながっています。
経営体験報告では、その挑戦に至るまでの数多くの失敗も赤裸々に語られ、今までもそしてこれからも理念を追求し続けていかれる覚悟を強く感じることができました。
報告を受けてのグループ討論も大いに盛り上がり、グループごとにさまざまな考え方や捉え方が示されました。当日は(株)障碍社の社員さんだけでなく、神奈川同友会からも多くの方が参加され、地域や立場を越えた意見交換ができたことで、例会の学びがさらに深まったと感じています。
それぞれの会社に学びを持ち帰り、共に良い会社づくりを進めていきましょう!
参加された方の声
例会報告から学んだこと、感じたことなどを率直にお書きください。
意思決定のない、選ばされた自己選択、自己決定があるということは気づかなかった。
自分の強みを知る機会。特徴に対する知識。知っているだかで、相手を理解しようとする、気づくきっかけを、持てる。強みを生かす場を作る
障害者雇用の意味と意義について知る機会となりました。
ご報告のようなみんなが幸せになる仕組みを考え、自己選択、自己決定、自己責任を行動に起こしたいと感じた。
非常にいい学びでした!
ジャムの法則新しいこと1つ持って帰ります!
人を生かす経営の大切さを実感いたしました。
優れたビジネスモデルを知り、同時に障碍者を含めた共生について自分でも改めて考えることができて大変よかった
うちの社長の発想はすごい!
とついて行きたくなるビジネスモデル。
前向きに捉えるを大切にします
自分が決めれたことがよかったです。
想像を超えたお話でよかったです
小さい頃からのチャレンジ、失敗することの体験が、考えることを育てていくんだなと感じました。会社でも、どんどんそういう環境を作っていくことが大切。ジャムの法則にあったように、情報が多いと、悩みも多いので、経営者としての器を広げたいと思いました。
利用者とヘルパーさんとの関係性を考えさせられるお話でした。高齢者介護では、考えられない仕組みだと思いました。
各企業の会員の方がとても熱く討論していた。とても良かった
人材育成の大事さ
仕事とはじぶんのためだけでなく、仲間や社会と共に生きるためにあり、その中で培われる自己選択自己決定自己責任の姿勢が人を生かし社会を強くすると、学びました。
同業ではありますが、全くの逆転の発想で業績を伸ばしているところに驚きました!
奈良でも同じように当事者の方が立ち上げている事業所もあるにはあります。しかし、ここまで本人のエンパワメント着目して循環させている事業所は見た事がなく、利用者が利用者を育て次の利用者へ恩送りをするシステムと、人を信頼して育てる経営に感銘を受けました。
グループ討論では共生という言葉にひっかかってしまう場面があったのでもったいなかったですが、障害のあるなしに関わらずコミュニケーショや、聞く力、伝える力をお互いが養う事が大事だという話に改めて共感しました。
一方的な経営でなく、お互いが知恵を出し合い思い合う、そんな経営者である事が業績を伸ばすヒントであると感じました。
障害者雇用で大事なのは、じっくり進める。焦らない。長い目でみる。いいところを伸ばす。
ハラスメントに気をつける。何気ない一言が信頼を崩す。考えるということが大事。考えてばっかりではダメだけど、考えて工夫して、それの連続。それが自己責任につながる。
社会と共生しながら自分らしくいきるために3つの責任とは?会社で実践する場合は、社員に寄り添い、フォローし合う関係性が大切ですが、その前にしっかり信頼関係を構築させるなどの意見がだされました。挨拶を笑顔でかわす。丁寧に対話するなど、確認をしました。自分で選択できる喜びを達成したときにはひとつステップUPし自信につながりますし、互いに人として成長する。お時間はかかりますが、面倒くさいことを穏やかに丁寧に言動していきたいです。
人はひとりでは成長せず、だれかと関わる中で成長しますので、社会で共生しながら自分らしくいきるためには、学び続けることだと思いました。
ご自身の困り事をご自身の知識•学識や興味関心で解決したことが、社会課題の解決に大きなインパクトをもたらした。そのことが、安藤さんの「社会との共生」なのだと感じました。収益が補助金•助成金に限られている前提で、ビジネスモデルを理解するのが難しかったです。
グループ討論では、討論テーマが抽象的すぎたのか、このテーマを深めることが難しかったように感じます。障害者•健常者に関わらず「社会との共生」をそれぞれがどう捉えているのか、そこから共有できていれば…と、帰り道に考えていました。
自分らしく生きるというのは、誰かに社会で必要とされることだと改めて気付いた。
自分だけが生きがいを感じるのではなく、人にも感化できるようになりたいと思う。
真面目に経営を学ぼうとしている経営者の方々が、こんなにたくさんおられることにびっくりしたと同時に感動しました。
どこの事業所・会社にも発達障害の方々がいると思いますので、その方々の特徴を社員のみんなが理解できれば、その会社は発展していくはずです。
”決める”ということの重要性
決める・決めさせることが、自分を会社を動かすのだと思いました。
自分で考えることで楽しく思う
社会と共生という自分らしく生きるため!
まずは、決めるということが大切
多様性社会の中で、いかに自分らしく生きていくのか?
いかに人を生かしていくのか?
考えるいい機会になった
共生の意味を考えられた
「人事ポリシー」があることで、多様な人材を言語化にて守られている職場と想像しました。
障がいがあってもなくても、自分の責任で自分のことを決めていくことは、人生を自分でコントロールできていると実感できそうだと思いました。
ピアサポートの意義も共感しました。
パーソナルアシスタントが日本で根付いていくために、いろいろな挑戦をされているとのこと。自立生活運動の内実を知る事ができました。
報酬(国の)の低さが大きな根本原因と思います。福祉制度の改善をあわせて安定経営につながりますよね。