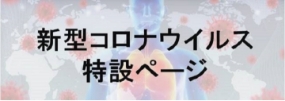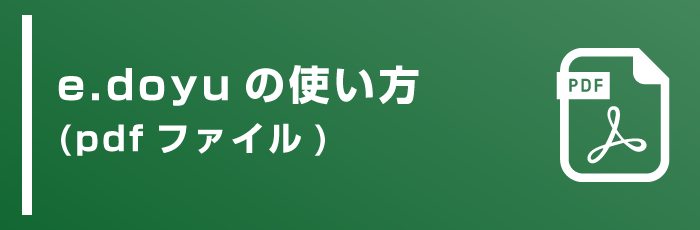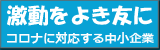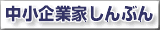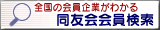同友会とは
中小企業家の皆さんの
あらゆる悩みにこたえ
共に解決する集い
それが中小企業家同友会です。
異業種の経営者の集まりの中から、
自由な交流・議論
が行われ、
強じんな経営体質をつくることを
目的としています。
同友会3つの目的
よい会社をめざそう
よい経営者になろう
よい経営環境をつくろう

社会から、あてにされ、社員が生きがいを持って働き、永続して利益を出し続ける企業。
そのために経営者は、謙虚な学びから、人格的成長をめざし総合的な能力を身につけることが求められています。
また、中小企業の置かれている環境に注目し、進んでその改善に力を注ぐことも大切なことといえます。
自主・民主・連帯の精神
いかなるところからも干渉も受けず、会員の自主性を大切にする
一部の人間の支配を避け、民主的なものの見方をあらゆるところで実践することを大切にする
会員同士の援け合いと外へ向けての協力団結を進める
特に会内においては、お互いの人格的高まりあいから生まれる深い信頼関係で、連帯を築く
国民や地域と共に歩む中小企業
社会的使命感と責任感を大切にし、反国民的行動は決してとらないことが求められます。
また、自社の所属する地域の発展こそが、自社の生きる道であることを深く認識し、
人材の育成はもとより、地域活性化のための社会的な運動に参画し、
金融アセスメント法の推進など、
地域経済の発展に寄与していかなければなりません。
全国に約47,000社が加入
中小企業家同友会は、日本すべての中小企業の繁栄と、
そこに働くすべての人々の幸福をめざして、
1957年(昭和32年)4月に設立されました。
今では、47都道府県すべて(会員数約47,000社)に広がっています。
同友会の特徴
- CHARM 悩みや課題を持つ経営者が相互の経営体験を交流し、
「一人ひとりが会の主人公」「お互いが教師であり生徒である」という謙虚な姿勢で学びあう - CHARM すべての業種が集まる異業種の経営者団体
- CHARM 会員の自主性を尊重し、知り合い、学び合い、たすけ合いを日常的に追求
- CHARM 財政は、会費を中心とした会員からの収入で成り立ち、中小企業家(会員)が手づくりで運営
- CHARM 個人の思想・信条、社会的地位、企業の大きさ、新旧に関係なく、
対等・平等に意見や要望を出し合い、相互理解のうえで運営 - CHARM 特定の政党を支持せず、どの政党とも分け隔てなく接触し、会員個人の思想・信条の自由を保障
同友会で行うこと
行事・例会

会員による、生きた経営体験の報告
同友会では「会員は辞書の1ページ」と言われています。つまり百人百様の異なる経営体験があり、そこから学びあうことが経営者としての生きた学びになります。
同じ悩みを持つ経験者のリアルな経営体験の報告は、業種を超えて学び合うことができます。また成功体験ばかりでない、課題に取り組む過程や悩みの中身にせまることこそ、経営の本質的なヒントを見つけることになります。
自社の経営課題を掘り下げて、討論する学びの場
同友会例会の最大の特徴は、教える教わるという立場がなく、互いに「学びあう」ことにあります。その学びあいの入口が例会です。
例会の報告者は、講師というよりは問題提起者です。報告者の経営体験から「あなたはどうですか? あなたの会社はどうですか?」という投げかけがされているのです。自分や自社に置き換えて考えることで、自社の経営課題を深く掘り下げられる機会となります。
本音で語り合い、ともに解決の糸口を探る場
報告を聞いたあとには、テーマを基にした討論(グループ討論)をおこないます。グループ討論では、自ら発言するだけでなく、同じグループの参加者の話を聴きなが ら、テーマに即した学びを深めます。自分とは異なったとらえ方をした意見や、討論のやりとりの中から考え方の違いを理解し、その良さを受け入れることができます。
そして互いに真剣に経営に向き合う者同士が本音で語り合うことで、新たな気づきや解決の糸口を得るきっかけも生まれます。
例会
生きた経営体験報告から
自社の課題や悩みの解決に繋げる学びの場
会員による「生きた経営体験報告」
経営者には誰でも悩みや課題があります。それを持ち寄り、他の経営者の
失敗談やリアルな経営体験を聴くことで、新たな気づきや学びを得ます。
例会運営と報告者の学び
例会の企画
会員みんなの気づきや学びになるような目的を設定します。
報告者の選出
目的に沿った報告者を会員から選出します。
プレ報告
リハーサルを行います。納得できる伝え方を学べる機会がプレ報告です。
例会の実施
自社の経営報告を通じて、自社を見つめ直し、新たな気づきが生まれます。
フィードバック
例会終了後、アンケートや、直接の声から、さらに見えなかった課題が見えてきます。
グループ討論
年齢や役職、会社の規模に関係なく
同じ目線で、経営の悩み•課題を討論し、
得た気づきや学びを深めます。
学びを自社で実践
気づきや学びをそのままにせず、
実践することで、解決の糸口が見えたり、
また新たな課題に気づきます。
経営指針づくり
経営指針は「経営の羅針盤」
同友会が目指す「よい会社」とは、企業の理念が明確であり、顧客や取引先からの信頼も厚く、社員が生きがいをもって働き、永続して利益を出し 続ける企業です。
同友会では、よい会社づくりの柱として「経営指針の成文化」を提起しています。経営指針の確立と実践こそが、会社という名の船が荒波をも超え て進むための羅針盤になるのです。
経営指針の成文化
経営指針とは「経営理念」「経営方針(戦略)」「経営計画」の3つを総称したものです。
会社の方向性は自分の頭の中にあるさ、ではなく成文化して社内で共有することは、以下のような効果があります。
経営指針(理念・方針・計画)をセットで成文化することで、企業経営に対する経営者の姿勢が明確になり、経営者自身の生きる姿勢の確立と使命感、意欲を高めることが出来ます。
企業の社会的存在意義や役割・性格・将来ビジョンが明確になるため、労使の信頼関係が高まり、社員が企業に誇りを持ち、働く意欲の増進につながります。
計画的・戦略的な採用計画を描くことで、優れた人材の採用が可能になります。
目指すべき社員像が具体的になり、社員教育の計画・実践も方向性が定まることから、自主的に学ぶ気風を職場に定着させることが出来ます。
顧客・取引先・銀行等、対外的にもイメージアップと信用力アップを図ることが出来ます。
経営指針成文化セミナーの内容
奈良同友会では、3か月にわたる全6日間のスケジュールで経営指針成文化セミナーを開催しています。
セミナーは
- CONTENT 経営理念の策定
- CONTENT 自社分析や市場分析を行った上で、経営方針(戦略)の策定
- CONTENT 中期経営計画、単年度経営計画の策定
という内容で進められます。
毎回、課題も多く出されてハードな内容にはなりますが、その分今後の経営をどのように進めていくべきかを明確にすることができます。
また苦労をともにした同期受講の経営者は、セミナー後も互いにフォローアップの機会を設けたり、経営のよき相談相手になるなど、交流が深まっています
同友会3つの学び
生きた経営実践を通して「学びあう」
「問題意識を研ぎ澄ます」
×
「学び方を学ぶ」
×
「実践する」
同友会における日常活動の最大の特徴は「学びあう」ことにあります。
悩みや問題に対して前向きに解決のヒントを得たい。
それには、同じ中小企業家として共通の立場で努力し、
成果を上げている方から学ぶのが一番です。
同時代を生きる経営者として共通の土俵におきかえ、自社と対比させ、自社に何をどう取り入れるかという姿勢でのぞむことです。
そのためには、常に問題意識を研ぎ澄ましておくことでしょう。
問題意識の鋭さ、自社に必要なものを取り入れようとするどん欲さが「学ぶ力」になります。
また同じ話を聞いても聞き方=学び方の違いがあり、そこから「学び方を学ぶ」ことができます。
学んで実践、成果を上げ、そのことをまた同友会で報告し検証する、
このサイクルが企業を良くしますし、また同友会の活性化の原動力です。
同友会がめざす企業像
-21世紀型企業-
自社の存在意義を改めて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、
国民と地域社会からの信頼や期待に高い水準で応えられる企業。
社員の創意や自主性が充分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ちあい、
高まりあいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業。

入会のご案内
よい会社、よい経営者、よい経営環境を目指す方、
ぜひご入会ください!
同友会は、入会・退会、
行事への参加も自由です。
自律ある主体性を大切にしています。
中小企業家であれば企業規模、業種、資本金などに関わりなく入会できます。
こちらを御覧ください