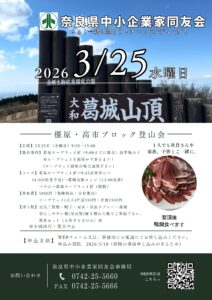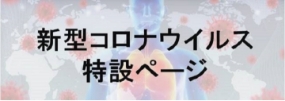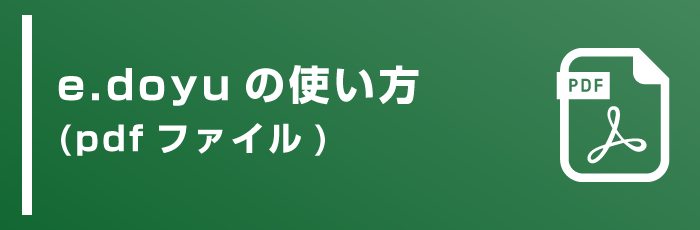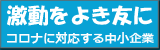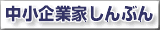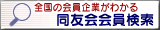参加された方の声
特に印象に残った内容を教えてください
伝える時の向きの話が参考になった。
横並びと正面をうまく使い分ける。
社内ではどうしても役職の違いなどにより
威圧的になったりしてしまうが、そういった場づくりが
必要だと感じました。
否定的現象の中から肯定面を見出す
“認めること”の重要性。どうしても自分の価値観を押し付けがちだが、その子なりに努力していることを認めていきたい。
褒めるではなく認める。これにつきます。
誉めるは 誉め殺し。認めるはその子なりに頑張ってることを認める。
ニュースを読む学生が減っている
育つのは子ども
育てるのではなく、育つ環境、関係性を作ることだと改めて感じた。
非効率を内包した最適解が存在しうることを痛感したこと。どうしても効率を追い求めすぎてしまうので、本質を見失わないようにしたいです。
一期一会。一緒にまなぶ。10年単位で人を見る。
文化を食べる。
先回りすること、待つことのバランスは、改めて難しいことと考えさせられました
・同じ方向を向いて話す
・助けてと言える先が沢山あるように
・心の扉を外側から開けない
・認めることの大切さ
・人間観を鍛える
・褒める⇒認める
いつも思っていることです。
褒めて伸びる人もいれば、褒めるとそれでもういいとなら場合もあります。また、うまく 褒めないと、ちょっとわざとらしく受け取られてしまうこともあります。
失敗した場合、褒めるというより、チャレンジを認める共に検討することで、次につながると思っています。
・絵本「ちょっとだけ」
即購入しました。楽しみです。
褒めるではなく認めるということ。後ろから推し放つ、ということ。
一番印象に残ったのは、質問コーナーの回答で、めんどくささを生きる手応えに変えること、最も手のかかる子を愛おしく思えるか、10年単位で人を見る、非効率な部分を抱えながら前に進むという部分に感動し、あたたかい気持ちになりました。
すばらしい機会をありがとうございました!
デジタル化が進む現代社会では、自然の中で育つこと(経験)不足になるだけでなく、テレビや新聞を見ない子どもが多く、社会への関心が希薄になっている。
一部の情報だけを見ていると考え方が偏ってしまいがちになるため、自分で考え、情報をつないで考える必要がある。
また自分とは違う考え方(批判)は、次へのステップである。
心の扉の取っては内側にあり、相手の想いを聴くことが大切。
待つということの難しさはこちらが試されている。面倒くさいと思う事を生きる手応えにかえる…
自分の人間力を問うという事を聞かせていただき、自分を振り返る機会となった。
要求の二重構造のお話がとても印象に残りました
優しさを刻む、信頼無くして安心無し、安心無くして対話無し。
自分が支えられているか?待てれるか?
心の扉は内側にある。
人間性の尊重、人間の尊厳
「生きてて良かった!」「今こそ楽天力」
自分の人間力を高める良い機会となりました。ありがとうございました。
コミュニケーション、会話は対面ではなく、横並びで…を実践してみようと思った
待つことは耐えること。→自分の人間力が養う 共に育つ →楽しむ事
”生産性”ばかりを追わない、経営計画と評価基準。
新しい発想で生産性を越えていく目標設定が必要
困った子は、困っている子→誰ひとり取り残さない 包摂の世界を目指したい
手をつなぐというお話しがよかった
川柳が面白かった。両方役に立ちます。
子どもの手のつなぎ方が3つあるということ。
ひとつひとつ子どもと向き合い、同じ目線、同じ方向
共育 自分の頭で考える力
めんどくささを楽しみに変える 自分の人間観を鍛える
共に育つ意識は常に持っておきたいです。
人を動かしたい気持ちが出たら、ちょっと視点を変えてみること!
待つことでその先を見てみたいです。
要求の2重構造 何でも先々やってしまうので、子どもの自立の為、待つことが大事
昔、よく娘に「巻き戻し!」と言われていたのですが、要求の二重構造だったのかなと思いました。
どうしても親目線で子供を育ててしまっていますが、自立するために親は後押ししてあげるというのが心に響きました。
子育てだけでなく、会社でも活かしていきたいと思います。
ありがとうございました。
先生のお話しを聞かせていただいて、「(発達)保育の主体は子どもである」ということをさらに実感しました。
子どもの主体性を育てる・生きる力を育てるために、子ども自身が選べる環境(自己決定)・能動的な意欲ある存在(能動性)・自尊感情を育てる・一人一人を大切に(個別性)が重要。
”未完の喜び”のお話し、とても分かりやすかったです。便利性、生産性、効率性が気になる日々(社会)ですが、改めて日々を見直す機会となりました。
何をおいても人間性を磨くことが大切だと思いました。
実践を通してのお話し、ありがとうございました。
レジメ、帰ったらゆっくり拝読させていただきます。
山本先生の子育て、我が子の時に「助けて」と言うということに救われた気がしました。
また、共育ちということで、「トラブル」のときが子どもの育つとき、親も育つときだと考えることで、光が見え、またがんばっていこうと思いました。
心の扉の取っ手は、内側にあり外側からは開けないという言葉が心に残りました。
自己満足での導きはやめて、少し待つという事をしてみたいと思いました。